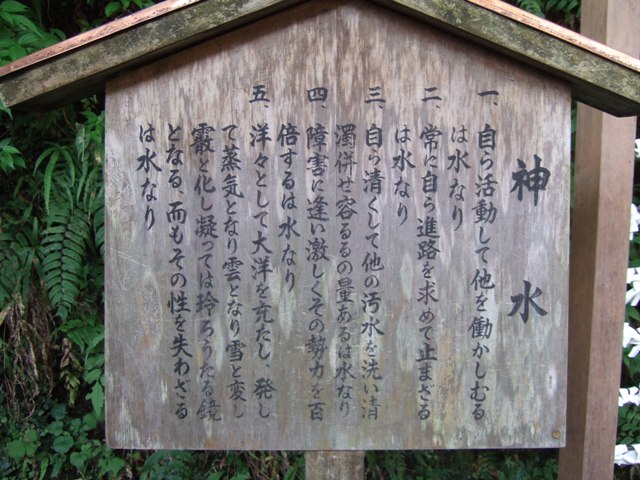(ن»¥ن¸‹م€پهچکè،Œوœ¬م€ŒTo be yourselfم€چمƒ´م‚£مƒ¼مƒٹم‚¹م‚¢م‚½م‚·م‚¨م‚¤م‚·مƒ§مƒ³ه‡؛版م€€م‚ˆم‚ٹه¼•ç”¨ï¼‰
ه›½é€£é£ں糧農و¥و©ں関(Fï¼،O)مپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پ2001ï½2003ه¹´مپ®é£¢é¤“(و „é¤ٹن¸چ良)ن؛؛هڈ£م‚’ه¹´é–“ه¹³ه‡8ه„„5400ن¸‡ن؛؛مپ¨وژ¨ه®ڑمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚و—¥وœ¬مپ®ن؛؛هڈ£مپŒمپٹم‚ˆمپ1و†¶ï¼’ï¼—ï¼گï¼گن¸‡ن؛؛مپ§مپ™مپ®مپ§م€پن¸–ç•Œمپ§مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®ه…¨ن؛؛هڈ£مپ®ï¼—ه€چه¼±مپ®ن؛؛م€…مپŒم€پو „é¤ٹن¸چ良م‚„飢مپˆمپ§è‹¦مپ—م‚“مپ§مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپ†مپ،8ه„„ï¼’هچƒن¸‡ن؛؛مپŒم‚¢مƒ•مƒھم‚«م‚„و±هچ—م‚¢م‚¸م‚¢مپھمپ©مپ®é–‹ç™؛途ن¸ٹه›½م€پ2500ن¸‡ن؛؛مپŒو—§م‚½é€£هœ°هںںمپھمپ©éپژو¸،وœںمپ«مپ‚م‚‹ه›½م€…م€پمپمپ—مپ¦900ن¸‡ن؛؛مپŒه…ˆé€²ه›½مپ®ن؛؛م€…مپ§مپ™م€‚
مپ¾مپںم€پمپمپ®مپ†مپ،3ه„„5هچƒن¸‡ن؛؛ن»¥ن¸ٹمپŒهگمپ©م‚‚مپںمپ،مپ§مپ™م€‚飢مپˆم‚’هژںه› مپ¨مپ—مپ¦و¯ژو—¥م€پ2ن¸‡ï¼•هچƒن؛؛مپŒه‘½م‚’èگ½مپ¨مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پمپمپ®مپ†مپ،5و³وœھو؛€مپ®هگمپ©م‚‚مپ®ه‰²هگˆمپŒï¼—ï¼’ï¼…م€پمپھم‚“مپ¨1ن¸‡ï¼کهچƒن؛؛مپ«م‚‚مپ®مپ¼م‚‹هگن¾›مپںمپ،مپŒé£¢é¤“مپ§و¯ژو—¥مپھمپڈمپھمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ن»ٹمپ“مپ†مپ—مپ¦مپ„م‚‹ï¼”ï¼ژï¼ک秒مپ®مپ†مپ،مپ«ن¸€ن؛؛مپ®هگن¾›مپŒم€پ飢餓مپ§مپھمپڈمپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھم‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚
هگŒمپکهœ°çگƒمپ§ç”ںمپچم‚‹ن؛؛مپںمپ،م€پمپ“م‚Œمپ مپ‘ه¤ڑمپڈمپ®ç§پمپںمپ،مپ®ن»²é–“مپںمپ،م‚„هگن¾›مپںمپ،مپŒم€پç©؛è…¹مپ§è‹¦مپ—مپ؟م€پ絶وœ›مپ®مپ†مپ،مپ§ن؛،مپڈمپھمپ£مپ¦مپ„مپڈمپ“مپ¨م‚’م€پمپ„مپ¤مپ¾مپ§م‚‚見éپژمپ”مپ™م‚ڈمپ‘مپ«مپ¯مپ„مپچمپ¾مپ›م‚“م€‚ç§پمپںمپ،مپ¯م€پن½•مپ¨مپ‹مپ“مپ®é£¢é¤“ه•ڈé،Œمپ«ç«‹مپ،هگ‘مپ‹مپ£مپ¦مپ„مپ‹مپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚‰مپھمپ„مپ®مپ§مپ™م€‚
مپ§مپ¯م€پمپ„مپ£مپںمپ„مپ©مپ†مپ—مپ¦م€پمپ“مپ†مپ—مپںو‚²هٹ‡مپŒèµ·مپ“مپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ†مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ںçڑ†مپ•م‚“مپ¯م€پمپ©م‚“مپھمپ“مپ¨مپŒçگ†ç”±مپ§م€پمپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھ飢餓ه•ڈé،ŒمپŒèµ·مپ“مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™مپ‹ï¼ںçœںمپ£ه…ˆمپ«è€ƒمپˆم‚‰م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپŒé£ں糧ن¸چ足م€‚ن¸–ç•Œمپ®ن؛؛هڈ£مپŒه¤ڑمپ™مپژمپ¦م€پهœ°çگƒن¸ٹمپ§ن½œم‚ٹه‡؛مپ™é£ںو–™مپ®é‡ڈمپŒè¶³م‚ٹمپھمپ„مپ¨مپ„مپ†çگ†ç”±مپŒو€مپ„مپ¤مپڈمپ®مپ§مپ¯مپھمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹م€‚
ه®ںمپ¯م€پمپ“مپ®è€ƒمپˆمپ¯م€پهچکمپھم‚‹ه‹کéپ•مپ„م€پو€مپ„è¾¼مپ؟مپھمپ®مپ§مپ™م€‚هœ°çگƒمپ®ç”ں産و€§مپ¯م€پç§پمپںمپ،مپ®وƒ³هƒڈم‚’مپ¯م‚‹مپ‹مپ«è¶…مپˆمپ¦ه¤§مپچمپڈم€پن¸–ç•Œمپ®ç·ڈé£ں糧ن¾›çµ¦مپ¯م€پçڈ¾هœ¨مپ§م‚‚م€پهœ°çگƒمپ®ه…¨ن؛؛هڈ£م‚’é¤ٹمپ†مپ«هچپهˆ†مپھé‡ڈم‚’ç¢؛ن؟مپ§مپچمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ن¸–ç•Œمپ®ç·ڈé£ںو–™ç”ں産é‡ڈم‚’ن¸–ç•Œن؛؛هڈ£مپ§ه‰²م‚‹مپ¨م€پن¸€ن؛؛ه½“مپںم‚ٹم€پو¯ژو—¥ï¼’kg程ه؛¦مپ®é£ں糧م‚’ن¾›çµ¦مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹مپ®مپ§م€پم‚‚مپ—وœ¬ه½“مپ«ن½™مپ™مپ“مپ¨مپھمپڈمپ؟م‚“مپھمپŒهڈ£مپ«مپ—مپںمپھم‚‰مپ°م€پç—©مپ›م‚‹مپ©مپ“م‚چمپ‹مƒ،م‚؟مƒœمƒھمƒƒم‚¯ç—‡ه€™ç¾¤م‚’ه؟ƒé…چمپ—مپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚‰مپھمپ„مپ»مپ©مپ®é‡ڈمپ§م€پن¸–ç•Œمپ¯م€پم‚€مپ—م‚چه¤ڑمپ™مپژم‚‹é£ں糧مپŒç”ں産مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚
مپم‚Œمپ§مپ¯م€پمپھمپœمپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھو‚²وƒ¨مپھ飢餓ه•ڈé،ŒمپŒèµ·مپ“مپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ†مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ںç´›ن؛‰مپھمپ©مپ®ن؛؛ç‚؛çڑ„çپ½ه®³م€پهœ°éœ‡م‚„و´¥و³¢م€پو´ھو°´م€په¹²مپ°مپ¤مپھمپ©مپ®è‡ھ然çپ½ه®³م€پ貧ه›°مپھمپ©م€پمپ•مپ¾مپ–مپ¾مپھçگ†ç”±مپŒهڈ–م‚ٹمپ–مپںمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™مپŒم€پوœ¬è³ھçڑ„مپ«مپ¯م€پهœ°çگƒمپ®è±ٹمپ‹مپ•م‚’هˆ†مپ‹مپ،هگˆمپ†مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¦مپ„مپھمپ„مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ«مپ¤مپھمپŒم‚‹مپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
ç§پمپںمپ،مپŒو—¥م€…وڑ®م‚‰مپ—مپ¦مپ„م‚‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¯م€په®Œç’§مپ§مپ¯مپھمپڈم€پمپ‚م‚ٹن½™م‚‹é£ں糧مپŒمپ‚م‚ٹمپھمپŒم‚‰م‚‚م€پمپم‚Œم‚’هˆ†مپ‹مپ،هگˆمپ†مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپڑمپ«م€پ飢餓مپ§و»ن؛،مپ™م‚‹ن؛؛م€…مپ«و‰‹م‚’ه·®مپ—ن¼¸مپ¹م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپھمپ„مپ§مپ„م‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚
م‚¢مƒ•مƒھم‚«مپ§مپ¯م€پم‚µمƒڈمƒ©هœ°و–¹مپ®ه›½م€…مپ§م€پï¼’ه„„1,300ن¸‡م‚‚مپ®ن؛؛م€…مپŒé£¢مپˆمپ«è‹¦مپ—م‚“مپ§مپ„م‚‹ن¸€و–¹مپ§م€پç››م‚“مپ«é£ں糧مپŒè¼¸ه‡؛مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚1960ه¹´ن»£وœ«مپ‹م‚‰70ه¹´ن»£هˆé مپ«مپ‹مپ‘مپ¦م€پè¥؟م‚¢مƒ•مƒھم‚«è«¸ه›½مپ§هڈ²ن¸ٹوœ€و‚ھمپ®ه¹²مپ°مپ¤مپ«è¥²م‚ڈم‚Œمپںمپ¨مپچم‚‚م€پ12.5ه„„مƒ‰مƒ«م‚‚مپ®é£ں糧مپŒè¼¸ه‡؛مپ•م‚Œç¶ڑمپ‘مپ¾مپ—مپںم€‚
مپ¾مپںم€په…ˆé€²ه›½مپ®م‚¢مƒ،مƒھم‚«مپ¯م€پن¸–ç•Œمپ®ه¯Œمپ®ï¼’5%م‚’و‰€وœ‰مپ™م‚‹ه¤§ه›½مپ§مپ‚م‚ٹم€پé£ں糧مپ«مپٹمپ„مپ¦م‚‚è±ٹمپ‹مپ§م€پو¯ژه¹´ç©€é،مپ®éپژه‰°ç”ں産مپ«é م‚’ç—›م‚پم€پ輸ه‡؛مپ«هٹ›م‚’ه…¥م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ»مپ©مپ®é£ںو–™ن¾›çµ¦هٹ›م‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ—مپ‹مپ—ن¸€و–¹مپ§م€پTheFreePress2003ه¹´12وœˆ19و—¥مپ®è¨کن؛‹مپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پç±³ه›½و°‘مپ®8ن؛؛مپ«1ن؛؛م€پç´„3,460ن¸‡ن؛؛مپŒè²§ه›°çٹ¶و…‹مپ§م€پمپ—مپ‹م‚‚م€پç´„3,100ن¸‡ن؛؛مپ®م‚¢مƒ،مƒھم‚«ه›½و°‘مپŒم€پو¬،مپ®é£ںن؛‹م‚’ه…¥و‰‹مپ™م‚‹و‰‹و®µم‚’وŒپمپںمپھمپ„م€Œé£¢é¤“çٹ¶و…‹م€چمپ«مپ‚م‚‹مپ¨ن¼مپˆمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
و—¥وœ¬مپ§مپ¯م€پ経و¸ˆçڑ„مپ«è±ٹمپ‹مپ§مپ‚م‚ٹم€پé£ںو–™مپ®ه¤ڑمپڈم‚’輸ه…¥مپ«ن¾هکمپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپمپ®è¼¸ه…¥é‡ڈمپ¯م€په…¨ه›½و°‘مپŒه؟…è¦پمپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹é‡ڈم‚’مپ¯م‚‹مپ‹مپ«è¶…مپˆمپ¦ه¤ڑمپڈم€پن¸–界1مپ®é£ں物輸ه…¥ه¤§ه›½مپ§مپ™م€‚مپںمپ مپ—م€پé£ں糧مپŒè±ٹمپ‹مپ§é£½é£ںمپ®وپ©وپµم‚’هڈ—مپ‘مپ¦مپ„م‚‹ن¸€و–¹مپ§م€پé£ںمپ¹هˆ‡م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپڑمپ«ه¤ڑه¤§مپھé£ںو–™م‚’وچ¨مپ¦مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚è¾²و°´çœپمپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پï¼’ï¼گï¼گï¼’ه¹´ه؛¦مپ®é£ںه“پ産و¥ه…¨ن½“مپ®ه»ƒو£„é£ںه“پمپ¯ç´„1,131ن¸‡مƒˆمƒ³مپ§م€په®¶ه؛مپ§ه‡؛مپ•م‚Œم‚‹ه»ƒو£„é£ںو–™مپ¨هگˆم‚ڈمپ›مپ¦2,300ن¸‡مƒˆمƒ³م‚‚مپ®é£ںه“پمپŒو®‹é£¯مپ¨مپ—مپ¦وچ¨مپ¦م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ¨ه ±ه‘ٹمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپمپ®é‡ڈمپ¯م€پن¸–ç•Œمپ®é£ںو–™وڈ´هٹ©مپ®ç·ڈé‡ڈم‚’ن¸ٹه›م‚ٹم€پمپ“مپ®é‡ڈم‚’م‚«مƒمƒھمƒ¼مپ«ç›´مپ™مپ¨م€پ途ن¸ٹه›½مپ®5,000ن¸‡ن؛؛هˆ†مپ®ه¹´é–“é£ںو–™مپ«هŒ¹و•µمپ™م‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚
مپ“م‚Œمپ¯م€پن¸€ن½“مپ©مپ†مپ„مپ†مپ“مپ¨مپھمپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ں
餓مپˆمپ¦ن؛،مپڈمپھم‚‹ن؛؛مپںمپ،مپ¯م€پمپھمپœم€پمپمپ“مپ¾مپ§è²§مپ—مپ„مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ں
çڈ¾هœ¨é£¢مپˆمپ§è‹¦مپ—م‚“مپ§مپ„م‚‹ن؛؛مپںمپ،مپ®70%程ه؛¦مپŒè¾²و‘هœ°ه¸¯مپ«ن½ڈم‚“مپ§مپ„م‚‹مپ¨è¨€م‚ڈم‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ§مپ™مپ‹م‚‰م€پهچپهˆ†è‡ھ給è‡ھ足مپŒهڈ¯èƒ½مپھمپ¯مپڑمپ§مپ™مپŒم€پç؟Œه¹´مپ®ç¨®هگمƒ»è‚¥و–™مƒ»è¾²è–¬مپ®è³¼ه…¥ï¼ˆçµ¶ه¯¾مپ«è²·م‚ڈمپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚‰مپھمپ„م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹ï¼‰م‚„ه€ں金مپ®è؟”و¸ˆمپھمپ©مپ®مپںم‚پمپ«م€پçڈ¾é‡‘هڈژه…¥م‚’ه¾—م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹم€پن½œç‰©مپ®ه¤§هچٹمپ¯م€پ輸ه‡؛مپ«ه›مپ•مپ–م‚‹م‚’ه¾—مپ¾مپ›م‚“م€‚مپمپ®çµگوœم€په½¼م‚‰مپ®ن½œç‰©مپ¯م€پمپمپ®ه¤§هچٹمپŒه…ˆé€²ه›½مپ«è¼¸ه‡؛مپ•م‚Œمپ¦م€په®¶ç•œمپ®é£¼و–™م‚„مƒگم‚¤م‚ھ燃و–™مپ¨مپ—مپ¦ن½؟م‚ڈم‚Œمپ¾مپ™م€‚ه½¼م‚‰مپ¯م€پن¸€ç”ںو‡¸ه‘½مپ«هƒچمپ„مپ¦م‚‚م€پè‡ھهˆ†éپ”مپŒé£ںمپ¹م‚‹مپ“مپ¨م‚‚مپ§مپچمپھمپ„مپڈم‚‰مپ„مپ®مپ”مپڈم‚ڈمپڑمپ‹مپھهڈژه…¥مپ—مپ‹ه¾—م‚‰م‚Œمپھمپ„مپ®مپ§مپ™م€‚
貧مپ—مپ„ن؛؛مپںمپ،مپ«وœ€ن½ژé™گمپ®ç”ںو´»م‚‚ن؟証مپ§مپچمپھمپ„مپ»مپ©مپ®ç”ںو´»م‚’ه¼·مپ„مپ¦مپ„م‚‹ن¼پو¥م‚„ن¸–界経و¸ˆم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¯م€پçڈ¾çٹ¶مپ®م‚ˆمپ†مپھ飢餓م‚’ç”ںمپکمپ•مپ›مپ¦مپ—مپ¾مپ†ن»•çµ„مپ؟مپ¯ه•ڈé،Œمپ§مپ‚م‚‹مپ¨وŒ‡و‘کمپ•م‚Œمپ¤مپ¤م‚‚م€پè‡ھ由競ن؛‰مپ®هگچمپ®م‚‚مپ¨مپ«م€پمپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھو‚ھه¾ھç’°م‚’و¢م‚پم‚‹مپ“مپ¨م‚’مپ—مپھمپ„مپ§م€پهˆ©و½¤è؟½و±‚م‚’貫مپ„مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚
مپمپ—مپ¦م€پوœ€çµ‚و¶ˆè²»è€…مپ§مپ‚م‚‹ه…ˆé€²ه›½مپ®ن؛؛مپںمپ،مپ¯م€پمپمپ®م‚ˆمپ†مپھéپژ程م‚’経مپ¦è¼¸ه…¥مپ—مپںé£ںوگم‚’م‚‚مپ¨مپ«مپ—مپ¦ç”ں産مپ—مپںه®‰مپڈمپ¦مپٹمپ„مپ—مپ„é£ںمپ¹ç‰©م‚’è‡ھç”±مپ«è³¼ه…¥مپ—م€پé£ںمپ¹مپچم‚Œمپھمپ‘م‚Œمپ°ه»ƒو£„مپ—مپ¦مپ—مپ¾مپ†مپ®مپ§مپ™م€‚م‚‚مپ،م‚چم‚“م€پم‚‚مپ¨م‚‚مپ¨مپ®è¾²ç”£ç‰©ç”ں産者مپںمپ،مپŒم€پمپمپ“مپ¾مپ§مپ®ه›°é›£مپ«مپ•م‚‰مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ¯çں¥م‚‰مپڑمپ«مپمپ®م‚ˆمپ†مپھمƒ©م‚¤مƒ•م‚¹م‚؟م‚¤مƒ«م‚’ن½œم‚ٹن¸ٹمپ’مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚
ç§پمپںمپ،مپ¯م€پمپمپ®مپ¤م‚‚م‚ٹمپ¯مپھمپڈمپ¨م‚‚م€پçڈ¾ه®ںçڑ„مپ«4.8秒مپ«ن¸€ن؛؛مپ®هگن¾›م‚’飢餓مپ§و»مپھمپ›مپ¦مپ—مپ¾مپ†م‚ˆمپ†مپھçٹ 牲م‚’途ن¸ٹه›½مپ«ه¼·مپ„مپ¦مپٹمپچمپھمپŒم‚‰م€پن¸€و–¹مپ§م€پمپمپ®هگن¾›مپںمپ،م‚’هچپهˆ†مپ«و•‘مپˆم‚‹مپ مپ‘مپ®ه¤§é‡ڈمپ®é£ں糧م‚’وچ¨مپ¦مپ¦مپ—مپ¾مپ†ç¤¾ن¼ڑم‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’ن½œم‚ٹن¸ٹمپ’مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚و±؛مپ—مپ¦و‚ھو„ڈمپ§ن½œمپ£مپ¦مپ„م‚‹م‚ڈمپ‘مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“مپŒم€پمپمپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¯م€پهڈ¤مپڈم€پو¬ 点مپŒه¤ڑمپڈم€پو©ں能ن¸چه…¨مپ«é™¥مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ¨è¨€مپˆمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
飢餓ه•ڈé،Œمپ¯م€په¤ڑمپڈمپ®ن؛؛مپںمپ،مپŒه•ڈé،Œم‚’èھچèکمپ—م€په¯¾ç–مپ®ه؟…è¦پو€§م‚’هڈ«مپ¶ه£°مپŒèچ‰مپ®و ¹مپ§ه؛ƒمپ¾مپ£مپ¦مپچمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ه‹ں金م‚„ه›½éڑ›و”¯وڈ´مپھمپ©م€په…·ن½“çڑ„مپھè،Œه‹•م‚‚èµ·مپ“مپ£مپ¦مپچمپ¾مپ—مپںم€‚مپ—مپ‹مپ—م€پé–‹ç™؛途ن¸ٹه›½مپ®é£¢é¤“ن؛؛هڈ£مپ¯و¸›م‚‹مپ©مپ“م‚چمپ‹م€پ1ه¹´مپ«400ن¸‡ن؛؛مپ®مƒڑمƒ¼م‚¹مپ§ه¢—مپˆمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ه•ڈé،Œمپ¯م€پو·±هˆ»مپ§م€پو ¹و·±مپڈمپ¨مپ£مپ¦م‚‚و‰‹ه¼·مپ„مپ®مپ§مپ™م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پن»ٹه¾Œمپ«هگ‘مپ‘مپ¦م€پمپ“مپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¯م€په¤‰مپˆمپ¦مپ„مپڈه؟…è¦پمپŒé–“éپ•مپ„مپھمپڈمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھو‚²هٹ‡م‚’ç§پمپںمپ،مپ¯è¨±مپ™مپ¹مپچمپ§مپ¯مپھمپ„مپ—م€پن»ٹه¾Œمپ«هگ‘مپ‘مپ¦م€پ飢餓ه•ڈé،Œم‚’م€په›½éڑ›ç¤¾ن¼ڑم€پوˆ‘م€…مپ؟م‚“مپھمپŒهچ”هٹ›مپ—هگˆمپ£مپ¦è§£و±؛مپ—مپ¦مپ„مپڈه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚